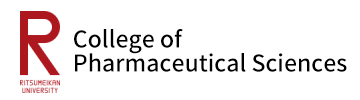NEWS & TOPICS
Japanese version only
2026.2.16
2026.2.16
林嘉宏教授の研究成果が本学の創発的研究支援事業HPで紹介されました。
立命館大学では2030年に向けた研究高度化中期計画のもと、若手研究者から中核研究者まで、研究者のキャリアステージに応じた支援と基盤的な研究支援にを行っています。
その一環として、科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業に採択された研究者が、創発的研究を牽引し、中核研究者として活躍できるよう、様々な支援を大学として提供しています。
今回、林教授が2025年7月に科学技術振興機構(JST)創発的研究支援事業として採択された「疾患特異的単球の同定に基づくサルコペニア発症機構の解明」の研究が紹介されました。
理工学部・小林 大造教授、薬学部・林嘉宏教授が、創発的研究支援事業における2024年度新規研究課題に採択 |立命館大学
2026.2.16
2026.2.16
R-GIRO研究教員・加堂ロディ准教授(分子薬物動態学研究室)の研究成果がプレスリリースされました。
分子薬物動態学研究室(藤田卓也教授)に所属され藤田先生と共に研究を進められているR-GIRO研究教員加堂ロディ先生の研究成果「血管を備えた「ミニ網膜」を、完全3Dプリント製チップ上で再現 —加齢黄斑変性の病態研究と創薬評価に向けた新技術—」がプレスリリースされました。
プレスリリース全文は本学広報課のHPを参照ください。
https://www.ritsumei.ac.jp/profile/pressrelease_detail/?id=1272
2026.2.16
2026.2.16
【3/12(木)】立命館大学薬学部シンポジウム〜データサイエンスと薬学〜を開催します。
2026.1.14
2025.12.24
2025.12.24
立命館大学薬学部第六回卒後教育講演会のお知らせ
第六回卒後教育講演会を実施いたします。
今回は「食と腸内細菌の関わりから考えるヘルシーエイジング」をテーマに、京都府立医科大学教授の内藤裕二先生を招聘し、講演を実施いたします。
参加無料となりますので、以下のURLからお気軽にお申し込みください。
※詳細は添付のチラシでご確認ください。
日時:2026年2月28日(土)11:10~12:40
※立命化友会会員(生命・薬の卒業生と教員)は懇親会(12:40~14:15)に参加可能です。
場所:TKPガーデンシティ京都タワーホテル7F 橘の間
講演:「食と腸内細菌の関わりから考えるヘルシーエイジング」
京都府立医科大学 教授 内藤 裕二 先生
<お申込み>
以下のURLよりお申し込みください。
https://forms.office.com/r/fsQSUT4mXM
※本講演会は、日本薬剤師研修センター受講対象(1単位)です。